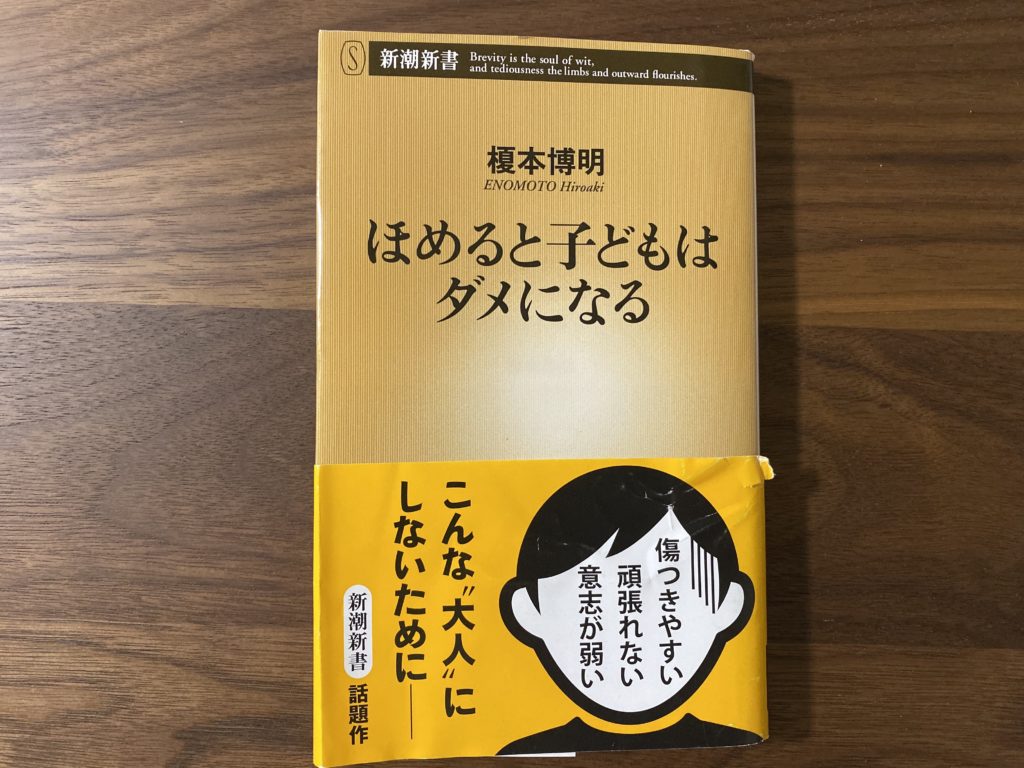
「子供をほめて伸ばす」「叱らない子育て」って本当に子供にとって良い教育なのか、ずっと疑問に思っていました。「ほめると子どもはダメになる(榎本博明)」を読むとそのモヤモヤの正体が言葉に置き換わって、少しすっきりしました。
目次
序章 なぜ「ほめて育てる」が気になるのか
序章では「ほめて育てる」子育てが広まった経緯と支持される要因、それによる弊害を提示しています。
「ほめて育てる」とか「叱らない子育て」といった標語をしょっちゅう耳にするようになった。その手の子育て本の代表のひとつである『尾木ママの「叱らない」子育て論』(尾木直樹、2011年)では、ほめられればだれだって嬉しいものだということを強調している。
同書より、以下を引用して疑問を投げかけます。
- 子育てのポイントは、“叱る”代わりに”ほめる”こと。
誰でも叱られるより褒められるほうが嬉しい。叱らないことがいいわけではない。嬉しがらせるのが子育てなのか。子どものご機嫌を取るのが子育てなのか? - 子どもとの約束は『石にかじりついてでも守る』。
守れそうな約束をして守ったら褒める、守らなくても叱らない。しかし、親は子どもとの約束は絶対に守るべきというが、なぜそこまで子どもを持ち上げるような子育てをさせようとするのか?
そして、同書の内容が必ずしも「叱らない子育て」を勧めているわけでもないと続きます。
叱るということに触れていないだけで、母親が本を読むとこどもに国語力がつくこと、「100点とったらごほうび」など条件づけがやる気を下げること、新しい問題集より一冊を何度も繰り返すのがよいことなど、非常に真っ当なことが書かれている。
では、なぜ本のタイトルや前書きで「叱らない子育て」をアピールするのか。それは、自分にも甘く子どもにも甘い親に受けるからではないか。
著者は「叱らない子育て」がもてはやされる背景として、以下を挙げています。
・子育てをラクしたい親、自己愛を満たしたい親にとって魅力的だから。
・メディアが叱る弊害を煽り、ほめる子育てを後押しする本やセミナーを売り込んでいるから。
・内容は真っ当だが、タイトルだけが一人歩きして、勘違いが世の中に広まっているから。
その結果、育った若者には以下の弊害があるとしています。
・失敗を怖れてチャレンジできない
・ゆるく生きるのに馴染みすぎて頑張れない
・教師や上司の注意や叱責に対してすぐに反発する
・些細なことでひどく落ち込む
・自分勝手な自己主張をする
・お客様扱いを当然とする
・褒められるのが当たり前
元々、厳しい子育てを行う父性社会の欧米から取り入れた「叱らない子育て」が、子どもに甘い母性社会の日本に表面的に取り入れられてしまったために、このような弊害が生まれたのではないかと提起します。
第1章 「注意されることは、攻撃されること」
この章では、ちょっとしたことで傷つき、反発し、社会適合に苦労する若者が出来上がる構造を説き、逆境に耐える力の育み方を提示しています。
「叱らない子育て」が推奨されるようになると、家庭ではもちろん子供を叱らなくなり、教育現場でも子供を叱ったりすると親からクレームが入るようになり、叱ること自体が敬遠されるようになります。
所属する社会のメンバーとしてふさわしい態度や行動様式を身につけさせることを社会化という。叱ることはその重要な手段となっている。
幼い子どもというのは、自然な状態だと衝動のままに動く。叱られることで、衝動のままに動いていてはダメなのだということをはっきり学び、社会的に望ましい行動パターンを身につけていく。
叱られることで社会性を身につけていた子供が、親や教師などから叱られなくなったことで動物のように感情のままに行動するようになります。
また、「ほめて育てる」教育は、子供の自己肯定感を高めるために推奨されましたが、調査データでは逆効果であったことを示しています。(著者が2012年に20代~50代の会社員700人に実施した調査より)
・年長者からアドバイスされて、うっとうしいと思うことがある(20代の3割)
・『上から目線』でものを言われてイラっと来ることがある(半数以上)
・人からバカにされたくないという思いが強い(半数以上)
・他人に批判されると、それが当たっていてもいなくても無性に腹が立つ(20代の4割)
望ましくないことをしても、義務を果たさなくても、厳しく叱られるということがない。そうした学校時代を過ごした者が社会に出ると、いきなり厳しい現実を突きつけられる。そこでの切り替えは難しい。
(略)
頭では理解できても、気持ちや身体がついていけない。叱られ慣れていない者にとって、叱られたときのショックは、周囲が思う以上に大きい。そのため、上司の正当な注意に対しても反発したり傷ついたりしやすい。
そこで思い通りにならない人生の逆境に耐える力、前向きに切り開く力として注目されているのが以下の性質を持つ「レジリエンス」という心理特性です。
・強いストレス状況下に置かれても健康状態を維持できる性質
・ストレスの影響を緩和できる性質
・一時的にネガティブな出来事の影響を受けてもすぐに回復して立ち直れる性質
もともとレジリエンスの研究は、逆境に強い人と弱い人の違いはどこにあるのかという疑問に端を発している。(略)
分かってきたのは、レジリエンスを高めるには、無菌室のような過保護な生活空間で育つのではなく、適度な挫折を繰り返し経験することが必要ということだ。そうした負荷がかかることで、いわば筋トレのように心が鍛えられていく。
両親が厳しさが子供のモチベーションの高さや粘り強さにつながるとも言います。
両親の厳しさと本人の心理傾向との相関をみると、父親が厳しいほど「有能になりたいという思いは人一倍強いほうだ」「失敗から学ぼうとする気持ちが強い」といった性質を肯定する傾向がみられた。そして、母親が厳しいほど「非常にやる気があるほうだ」「向上心が強いほうだ」「目標を達成したいという気持ちが強いほうだ」といった性質を肯定する傾向がみられ、「何事に対してもあまりやる気になれない」という性質を否定する傾向がみられた。
「友達のような母親」「良い母親=叱らない母親」という構図が定着し、叱ることに抵抗のある母親が増えており、公共の場で我が子を叱る母親を見て「ああはなりたくない」と思い、我が子がマナー違反しても自己保身のために叱れないと言います。
学校の通知表も以前は短所や改善を指摘する欄があったが、今は読み替えのテクニックで褒め言葉のみ書く傾向があり、子供に必要な助言を得にくくなっていると指摘します。
そして、厳しさの欠如によって「人為的ポジティブ状態」というミスをしてもまったく気にせず、同じようなミスを繰り返す大人を生み出すと警告します。
この手のタイプは、いくら注意しても染み込まず、「わかりました」と口では言うものの、深く受け止めないため、同じようなミスを繰り返す。ある意味でポジティブすぎて慎重さが足りないのだ。
(略)
至らない点があっても、修正すべき点があっても、そこをはっきりと指摘されずに、ほめられてばかりいたら、いつまでもそれらは修正されない。だから本人は自分の弱点や能力の現状を把握できず、勘違いだらけの人間になっていく。
さらに、「頑張ることができない心」を生み出すといいます。
子どもたちにイヤな思いをさせないためにできるだけ叱らず、良い気分になれるようにできるだけほめて育てようという姿勢が、あらゆる厳しさを排除する。勉強するにも子どもたちに強制するのはかわいそうだから、興味のない勉強を無理やりさせるのはやめて、できるだけ子どもの興味を引き出すように心がけようということになる。
(略)
ラクをしてできるようになりたい。努力しなければならないことはしたくない。好きなことはしたいけど、好きじゃないことはしたくない。楽しいならいいけど、苦しい思いをしてまでやりたくない。不愉快なこと、不快なことは我慢できない。そのような心をつくっているのが、「努力いらず」の文化を広めることで子どもの心から学びの体質を奪っていく大人たちなのである。
第2章 欧米の親は優しい、という大誤解
欧米から取り入れた「ほめて育てる」が失敗する原因として、欧米と日本の文化の違いを指摘します。
- 父性社会の欧米
能力や個性によって個人を区別するのは当然とみなされ、能力の乏しい者や成果を上げられない者は切り捨てられる。
勉強ができない学生は進級できず、退学させられ、仕事のできない社員は降格となり、クビを切られるのは当然。 - 母性社会の日本
個人が何らかの基準で区別されることはなく、能力の乏しい者も成果を上げない者も切り捨てられない。
学校では皆の能力を底上げして落ちこぼれを出さないことが重視され、会社ではできない社員を周囲がカバーすることが求められる。
父性社会では人々が強く有能な人間へと鍛えられる一方で、母性社会では協調的でやさしい人間が育まれると言います。
アメリカでは7割が体罰に賛成しています。
(略)キリスト教の思想も性悪説に立っており、子どもは厳しく、正しい道に導いていくべきと考えられている。その厳しさが行き過ぎて、1970年代までは子どもの虐待が目に余るほどであったため、子どもの人権を守る運動が起こった。その後、子どもに対する虐待防止が意識され、体罰より言葉で説得することが推奨されるなど、しつけの過酷さも提言してきているが、相変わらず父性の厳しさが強いのは文化的な特徴と言える。
親子別室の欧米では、赤ん坊のうちから身体的距離を作り出し、その物理的な距離を埋めるために乳児に盛んに話しかける言語的コミュニケーションを行うと言います。
一方、日本では常に親子は非常に近い距離を取り、心理的な一体感をもっているため、言葉を介さずに心はつながっているとし、
親子が切り離されず混然一体として溶け合っている日本的な母性社会では、ほめる前からすでに甘えによる心の交流がイヤというほど行われている。(略)そのため甘やかしが起こりやすく、厳しい父性をタテマエとして掲げることで、甘さを中和してきた。むしろ、心の中では子どもの活躍が嬉しくてたまらないのに何でもないフリを装うなど、言語的に距離を取ることでも、心理的密着の弊害を防いできた。
そこへ「ほめて育てる」思想が入って、子どもにとって最強の甘い関係ができあがり、子どもや若者の心の発達にさまざまな問題を引き起こしていると指摘しています。
日米の叱り方の違いについても言及します。
- アメリカの母親
子どもに有無を言わさずに言うことを聞かせる。
言うことを聞かないと、「食べなさい、食べなければダメ、食・べ・る・の」と次第に強制力を強める。 - 日本の母親
子どもになぜ言うことを聞かなければならないのか理由を説明したり、相手の気持ちに目を向けさせる。
言うことを聞かないと、「食べなさい、食べて頂戴、少しでいいから、明日は食べるね」と譲歩する。
子どもに対する譲歩は、アメリカ的には親としての権威の失墜、あるいは責任放棄ということになり、あってはならない態度とみなされる、と続けます。
ドロシー・ロー・ノルト共著『子どもが育つ魔法の言葉』から以下を引用し、
「一番大切なことは、親の同情を引けばわがままをとおせるのだと子どもに思わせないように注意することです」
ただ甘いだけの日本の親に警鐘を鳴らします。
友だち親子の関係も釘を刺します。
でも、弟は母に反抗することができず、友だち親子として行動を共にし、何でも話すというかかわりから抜け出すことができなくて、大学生になっても友だちができず、ついに引きこもってしまった。
親が子どもを囲い込むことで自立の足を引っ張ると言います。
そして、欧米のように親と子が別の個性と切り離されている文化と違い、親と子の一体感が強い日本の場合は「友だちのように何でも言える関係」が親と子の役割を希薄にし、親は社会のルールやマナーをきちんと教え込むことができず、子どもを甘やかすだけの結果につながるとします。
第3章 ほめても自己肯定感は育たない
この章では子どものモチベーションを上げる正しいほめ方と、叱り方について説明しています。
子どもの自己肯定感を高める狙いで取り入れられた「ほめる教育」が結果として自己肯定感の低下を招いているとし、本人の努力に見合っているかが重要だと言います。
ほめられることで自信がついても、脆い自信では意味がない。確かな自信、ほんものの自信とは、自分の必死の努力が実を結ぶことにより、自己効力感(自分はやればうまくできるという感覚)がしだいに高まってきて、永続的な自信になるということだろう。ほめられるだけでなく、そこには自身の努力の結実が欠かせない。
そうした努力なしに、ただほめられることでエネルギーを充電してもらうだけでは、すぐにエネルギーが枯渇するため、たえず称賛を求めることになる。それはほんとうの自信につながらないほめ方をされていることになる。
たいして頑張ってもいないのに褒められると、子どもは自信を無くす懸念があります。
教育心理学の領域ではほめることは言語的報酬を与えることと考え、それがモチベーションに与える影響について研究されており、以下のような褒め方をするとモチベーションを下げるとされます。
(1)易しい課題ができたときにほめると逆効果になる
(2)明確な根拠なしにほめるのは逆効果になる
(3)過度に一般化しすぎたほめ方をするのは逆効果になる
(4)コントロールするようなほめ方をするのは逆効果になる
また、努力ではなく「頭がいい」と才能を褒めると委縮し、失敗を回避するようになるという事例もあります。
- 頭の良さ(能力)をほめられた子ども
自分の能力の高さに対する期待を裏切りたくないという思いに縛られ、確実に成功しそうな易しい課題を選ぶ。
守りの姿勢に入り、チャレンジがしにくくなる。
勉強ができないことを、自分の頭の悪さや能力不足と考える傾向がある。 - 頑張り(努力)をほめられた子ども
努力する人間だという期待を裏切りたくないという思いに駆られ、次ももっと努力しようとする。
チャレンジしがいのある難しい課題を選ぶ。
勉強ができないことを、自分の努力不足と考える傾向がある。
多くのフランスの親もそうだけれど、彼女も、子どもが絶えずほめられて満足していたら、自尊心は育たないと信じている。(中略)子どもをほめすぎると害になることがある。親にほめられたい一心で、リスクを冒してまで何か新しいことに挑戦したいと思わなくなるからである」
(パメラ・ドラッカーマン『フランス人は子どもにふりまわされない──心穏やかに子育てするための100のヒミツ』)
失敗を受け入れられない子どもは、失敗から学ぶこともできなくなります。
失敗から学ぶことができるかどうかが、その後の失敗を防ぐことができるかどうか、その後に訪れる偶然のチャンスを活かすことができるかどうかを大きく左右する。その意味で、失敗から学ぶ姿勢を身につけることが重要となる。失敗から学ぶには、まずは失敗を受け入れる必要がある。失敗を認めることができないと、失敗から学ぶこともできない。
時に楽観主義より悲観主義のほうが成果を出すとし、
非現実的楽観主義者は、いくら注意しても染み込まず、「わかりました」と言うのに似たようなミスを繰り返す。ポジティブすぎて慎重さが足りないために成果が出せない。一方、防衛的悲観主義者は、ネガティブだからこそ慎重になり、用意周到に準備する。不安があり、ポジティブになれないことがじつは成果につながっているのである。
防衛的悲観主義の傾向を持つ相手に、「あなたの実力ならきっとうまくできる」とポジティブ思考を吹き込むと準備を怠って成績が悪くなるという事例を提示し、子どもの特性にあわせた褒め方が重要と示唆します。
親は子どもの基本的信頼感の獲得が重要とします。
親の温かいまなざしを感じることで、自分は愛されている、大事にされている、温かく迎えられていると信じることができる。それが人間に対する信頼、ひいては社会に対する信頼になっていく。同時に、自分は愛される価値のある存在なのだと感じることが、自分自身に対する信頼、つまり自信になっていく。
親から基本的信頼感を獲得できない子どもは生涯に渡る人間不信や自信のなさにつながると同時に、この基本的信頼感があれば厳しい叱責を行っても、子どもは一時的に反発したり落ち込んだりしても、いずれ立ち直り、成長の糧とし、親が自分を思って叱ってくれたと解釈できるようになるとします。
ここで求められるのは、「ダメなものをダメだ」と切り捨てる父性である。ときに子どもから見て理不尽な「ダメ」があっても、親は自分の価値観をぶつけることで子どもを鍛える。親の言うことを受け入れるにしても、それに反発するにしても、子どもの心はその「壁」によって鍛えられ、成長する。
そして子どもが傷つかないよう「ほめて育てる」方法だけでは、何も改善しないと結論づけています。
第4章 日本の親は江戸時代から甘かった
歴史的に見ても日本の親は子どもに甘いことを提示しています。
江戸時代の教育論者たちはそれぞれ以下のように言っています。
たとえば、貝原益軒は、日本で最初の教育論とされる『和俗童子訓』のなかで、(略)子ども可愛さのあまり美味しい物を与えすぎたり、厚着をさせたりすることで、かえって身体を弱くさせ、わがままにさせてしまうと戒める。
同時代の心学者、手島堵庵は、
子どもは親が厳しくするのは愛情ゆえだということがわからず、厳しすぎるとひめくれ者になってしまうので、やたらと怒鳴ったりせずに、静かに道理を教えるようにと説く。
その弟子の脇坂義堂も、
悪いことをしたときに折檻するだけだと、悪いことをしたときに折檻を怖れて隠すようになるだけなので、悪いことをしたときには温和に言い聞かせ、教え育てるのがよいとする。
そして、甘い親に対して厳しさを補っていたのが共同体の子ども組や若者組と言います。
若者組に入ると、厳しい戒律を守りながら社会的役割を担うようになるというのが一般的であり、その加入のために厳しい試練を課す儀式が執り行われることもあった。
明治後半から昭和初期あたりのしつけは地域と学校が担っており、親の影は薄く、「部落のしつけは厳しかった。部落のしつけを身につければ一人前であった」とされていました。
このような地域のしつけは今では完全に消滅しており、学校でのしつけも期待できない現代において、親のしつけが重要だと言います。
第5章 母性の暴走にブレーキを
「ほめて育てる」思想による「褒め過ぎ」は、発祥の地でも悪影響が指摘されているといいます。
最近の学生には「自分は特別」という思いが強く、忍耐力が低下していると指摘する。実際に、特別意識が強く、地道に頑張ることができないナルシシスト的な若者たちに訊くと、自分の親は甘く、自分をべたほめしたという者が多いという。
厳しい父性原理の欧米で「ほめて育てる」が甘やかしにつながるのであれば、父性原理が機能していない日本では一層深刻な影響が出るはずだとし、懸念しています。
もし完全に「ほめて育てる」を取り入れ、さらに弊害が起こらないようにするなら、親子関係の在り方も欧米流に変えていく必要がある。はたして私たち日本人にそれができるだろうか。
そして、そもそも日本流の子育てが欧米に劣るものではないと続き、
父性原理の厳しさを、ほめたりやさしい言葉をかけたりすることで中和しなければ子どもが厳しさに潰されてしまう欧米に対して、日本では母性原理のやさしさを、言語的に距離を取ることで中和しなければ子どもがやさしさの渦に呑み込まれて溺れてしまう。そうした文化的背景の違いを無視するわけにはいかない。
母性の暴走にブレーキをかけることが重要としています。
子どもが幼い頃に情緒的な絆をしっかりつくって子どもの心を安定させるという点では、日本の親の姿勢は非常に優秀といえる。ただし、問題なのは、いつまでも子ども扱いをして自立へと駆り立てることができないことにある。
物分かりの良い親ではなく、一方的な価値観をぶつけてくる親だからこそ、反抗によって心が鍛えられ、自立への希求に突き動かされて子どもは育っていくとしています。
物わかりのよい親というのは、子どもの意思を尊重したい、子どもの自由にさえてやりたいなどと言いつつ、結局子どもを鍛えるための子どもとの葛藤に耐える力をもっていないだけなのだ。そんな自分に甘い親が、子どもを路頭に迷わせている。自由放任の状態で、子どもは自分の価値観をどうやって鍛え、そして確立していくのだろうか。
日本文化に根づく湾曲的なしつけ方を再評価しています。
「おりこうだから、もうそんなことはしないよね」とか「いい子だね」というのは、けっしてほめているわけではない。よくなってくれるように期待を込めているのだ。そして、そうなることを信じている。なぜなら、日本人の心の深層には、他社の視線を裏切れないという姿勢が強く刻まれているからである。
何かにつけて「いい子」という言葉を投げかけることで、子どもに「自分はいい子だ」と思い込ませることで子供の中に「いい子だからこうしなければ」という自己規制を促し、ほめるのではなく日本的な歪曲的なしつけ方こそ適していると結び、最後に「熊の子別れ」を例に挙げ、厳しさこそ子育てに必要だと締めています。
感想
序章を読むだけで今まで抱えていたモヤモヤした気持ちが視覚化され、だいぶすっきりしました。
やっぱり変ですよね、叱らない子育て。
子供のご機嫌をとって甘やかしてばかりの子育てでは子供が真っ直ぐ育つとは思えません。むしろ我がままな自己中な大人にしかならないでしょ!ってツッコみたくなります。
欧米のように厳しい父親と優しい母親という役割分担ができていれば、母親は「ほめる教育」「叱らない子育て」に専念しても差し支えなさそうですが、日本の場合は父親も母親も甘くなってしまいうまく機能しなそうです。
社会にでれば理不尽なことばかりです。
その理不尽に心が折れないようにするためにも、子供に対して厳しく接するのは親にとってもストレスですが、「獅子の子落とし」という言葉もあるように、厳しさが子供の社会性を育て、自立を促し、失敗してもびくともしない打たれ強い子供にし、1人で生きていく強さを授けることができるのではと思いました。
また、なんでも褒めてしまうのは子どもの育成によろしくないことがわかり、褒め方についても勉強になりました。
才能ではなく努力を褒める。
努力し、見合った結果のときに褒める。
同情を引けば親が折れて我がままが通ると思わせないことも大事だなと思いました。法律やマナー違反はきちんと叱る。叱るときは簡潔に毅然と。できれば理由も述べる。
結局、子育てにおいて子供の「自立」を常に考えて行動することが大事だと改めて思いました。









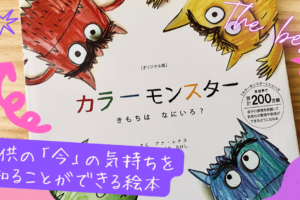


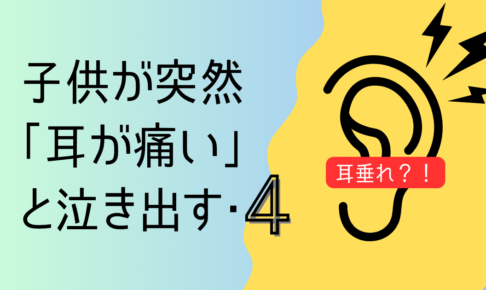
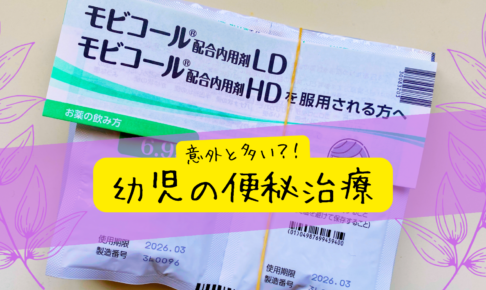



コメントを残す