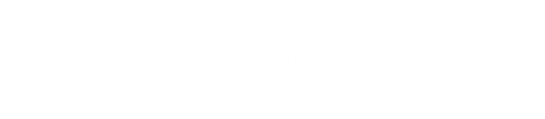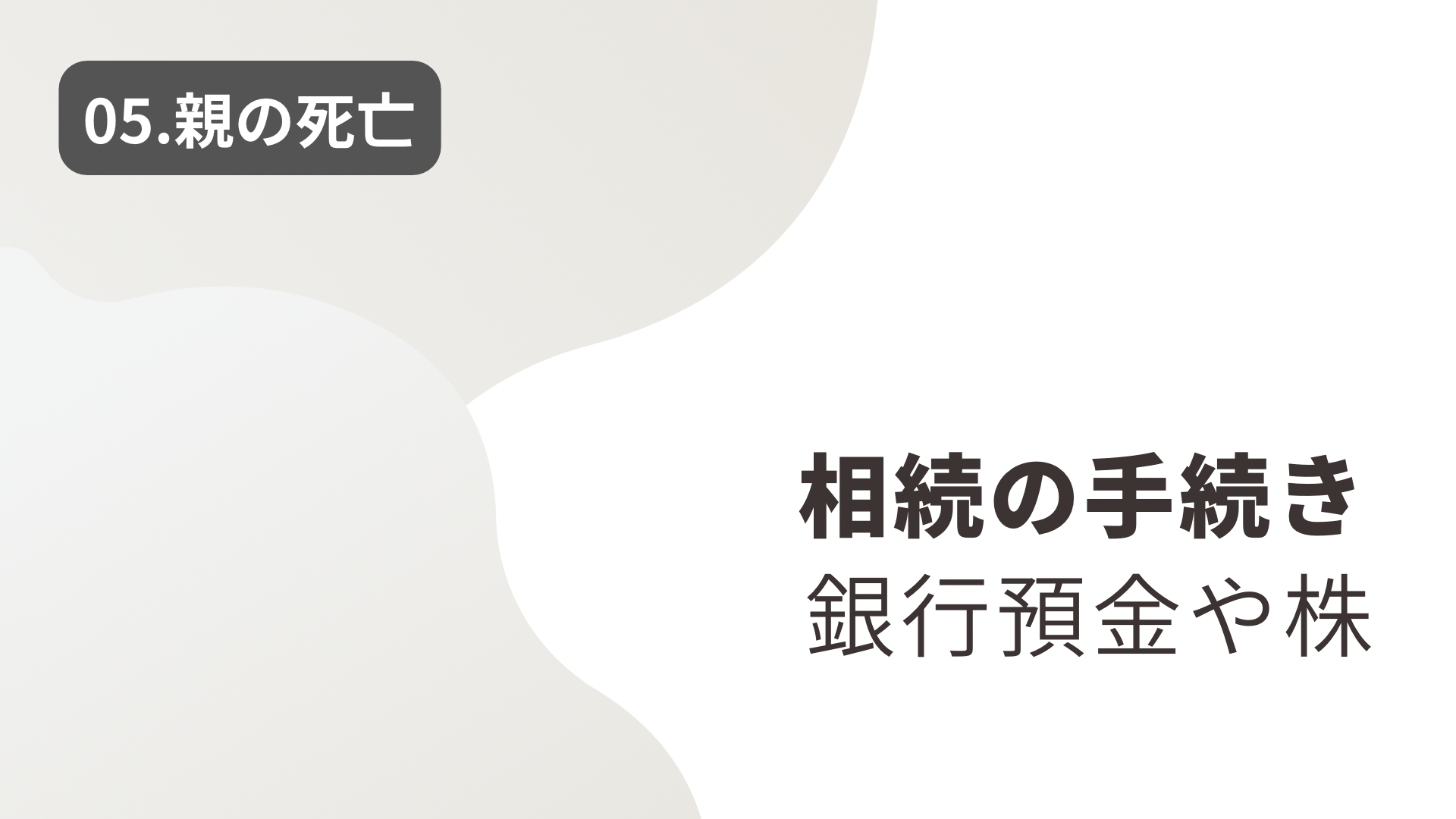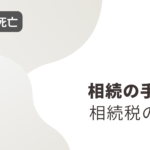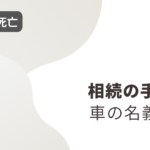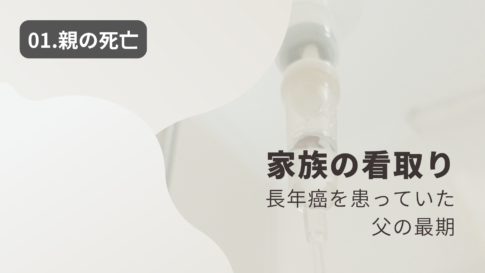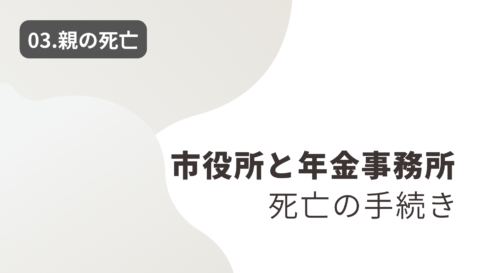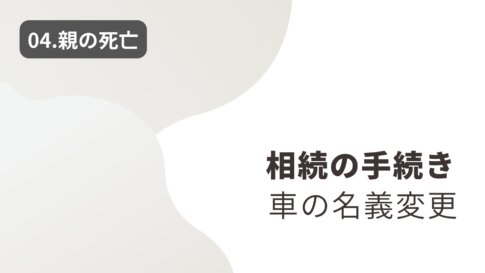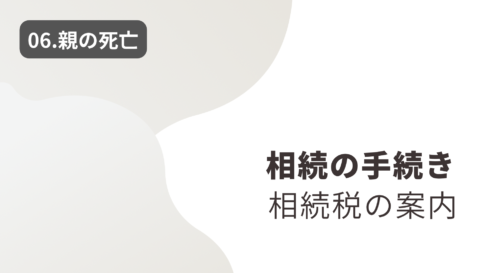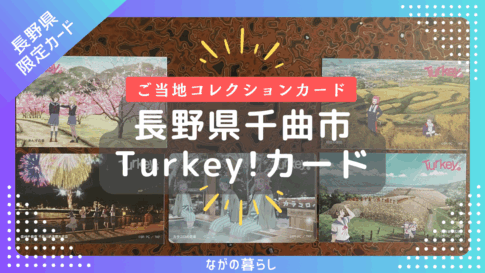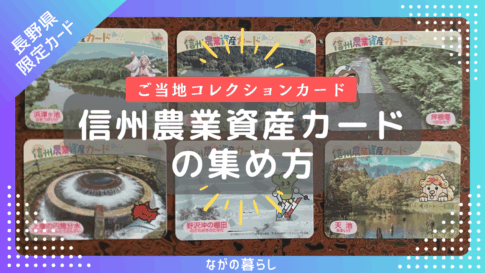死んだ父の預金や株の相続手続きを行いました。手続きにあたっては、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成し、手続きを簡略化しました。
目次
相続手続きを簡略化する「法定相続情報一覧図」の作成
銀行や証券会社などの金融機関で相続手続きを行う場合、相続人を確定するために、死亡した人の出生から死亡までの「戸籍謄本一式」をそれぞれ提出する必要がありました。
「戸籍謄本一式」は、父の場合で約5cmの厚みのある書類束でした。これを各金融機関ごとに提出すると郵送代や手間がかかって大変…
現在、「戸籍謄本一式」の書類束は「法定相続情報一覧図」1枚に置き換えることができるので、法務局で無料作成しました。
「法定相続情報一覧図」がある場合、どの金融機関でも相続手続きは以下の3点で行えました。
- 法定相続情報一覧図
- 印鑑証明書(相続人全員)
- 遺産分割協議書
「法定相続情報一覧図」作成に必要な書類
死んだ父の相続人は母・私・弟の3人で、申請は私が行い、必要な書類は以下でした。
- 死んだ父の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 死んだ父の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(住所の記載を行う場合)
- 申請人の写真付き身分証明書
母は父と同一世帯のため、死んだ父の戸籍謄本と住民票がそのまま流用できます。私と弟は、父や母と別世帯なため、それぞれの戸籍謄本と住民票を用意しました。
「法定相続情報一覧図」の元を自作する
「法定相続情報一覧図」自体は、Excelで自作します。
法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」からテンプレートをダウンロードして書き換えるだけです。
法務局に、自作した「法定相続情報一覧図」と必要書類を提出し、審査に合格すると、公式な「法定相続情報一覧図」として交付されます。
私の場合、以下の手順で作成しました。
作成手順
- 法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を開く
- 「法定相続人が配偶者及び子である場合」をクリック
- 「配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合」にある様式の「Excel」をダウンロードする
- Excelを開き、下部の「配偶者・子2人の場合」タブをクリック
- 黄色い部分に名前や住所を入力する
※戸籍謄本や住民票の記載と同一表記にする。
※旧字や番地表記などが一文字でも相違があると修正&再提出になります。 - 作成したものを印刷する
法務局で「法定相続情報一覧図」を申請と受取
長野県庁から信州大学教育学部に向かう途中にある法務局に行って手続きを行いました。
必要書類と作成した法定相続情報一覧図を提出し、私の顔写真付きの身分証を提示すると、受付票を渡されました。
特に問題なければ、受付の1週間後に「法定相続情報一覧図」を受け取ることができます。
私の場合、法定相続情報一覧図の番地の表記ミスと書類不備で2回ほど法務局へ足を運び、受付の1週間後に無事「法定相続情報一覧図」を受け取ることができました。
相続手続きの流れ
銀行の預金や証券会社の株券などは、各金融機関ごとに相続の手続きを行う必要があります。
主な相続手続きの流れは以下です。
- 相続手続きを開始する
- 預金残高を確認して、遺産分割協議する
- 相続手続きをする
①相続の手続き開始する
死んだ父はカード入れに銀行などのキャッシュカードをまとめいたので、それらの金融機関1つずつネットで相続手続きについて検索し、ネットや電話で連絡して相続手続きを開始しました。
- 住信SBIネット銀行
- SBI証券
- セブン銀行
- ゆうちょ銀行
どの銀行も相続手続きの専用フォームもしくは専用電話番号があり、連絡すると銀行口座が凍結され、相続手続きに必要な書類一式が郵送されました。(八十二銀行だけは窓口訪問必須)
②預金残高を確認して、遺産分割協議する
相続手続きを開始すると、預金残高などの相続情報の開示に必要な書類の提出が求められます。
- 法定相続情報一覧図
- 印鑑証明書
返信用封筒に上記の書類を入れて送ると、1週間ほどで預金残高と遺産分割協議書などが返送されてきます。
残高を確認して、どう遺産相続するか話し合います。なお、法律では配偶者が1/2、子供は1/4を相続と定めまれてます。
③相続手続きをする
我が家の場合、預金は母が相続することで話がまとまっていたので、遺産分割協議書の相続人に母がサインし、私と弟は相続放棄にサインして書類を返送しました。
株の相続の場合は相続人の証券口座が必要になるのでSBI証券に口座を用意してから、遺産分割協議書にそれぞれの口座番号を書いて返送しました。
1~2週間ほどで指定口座に振り込みなどが行われて、相続手続きが完了しました。