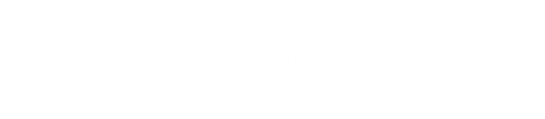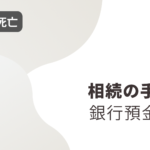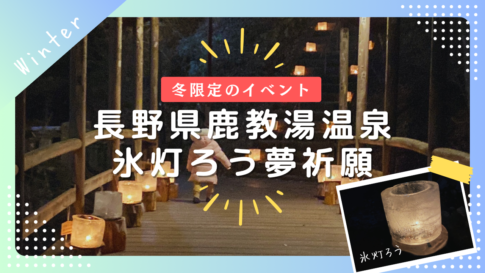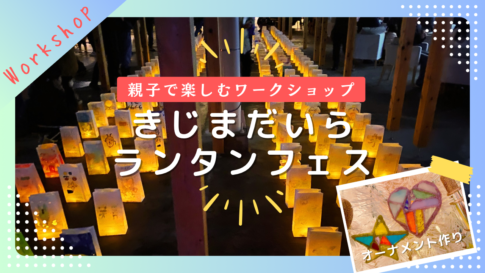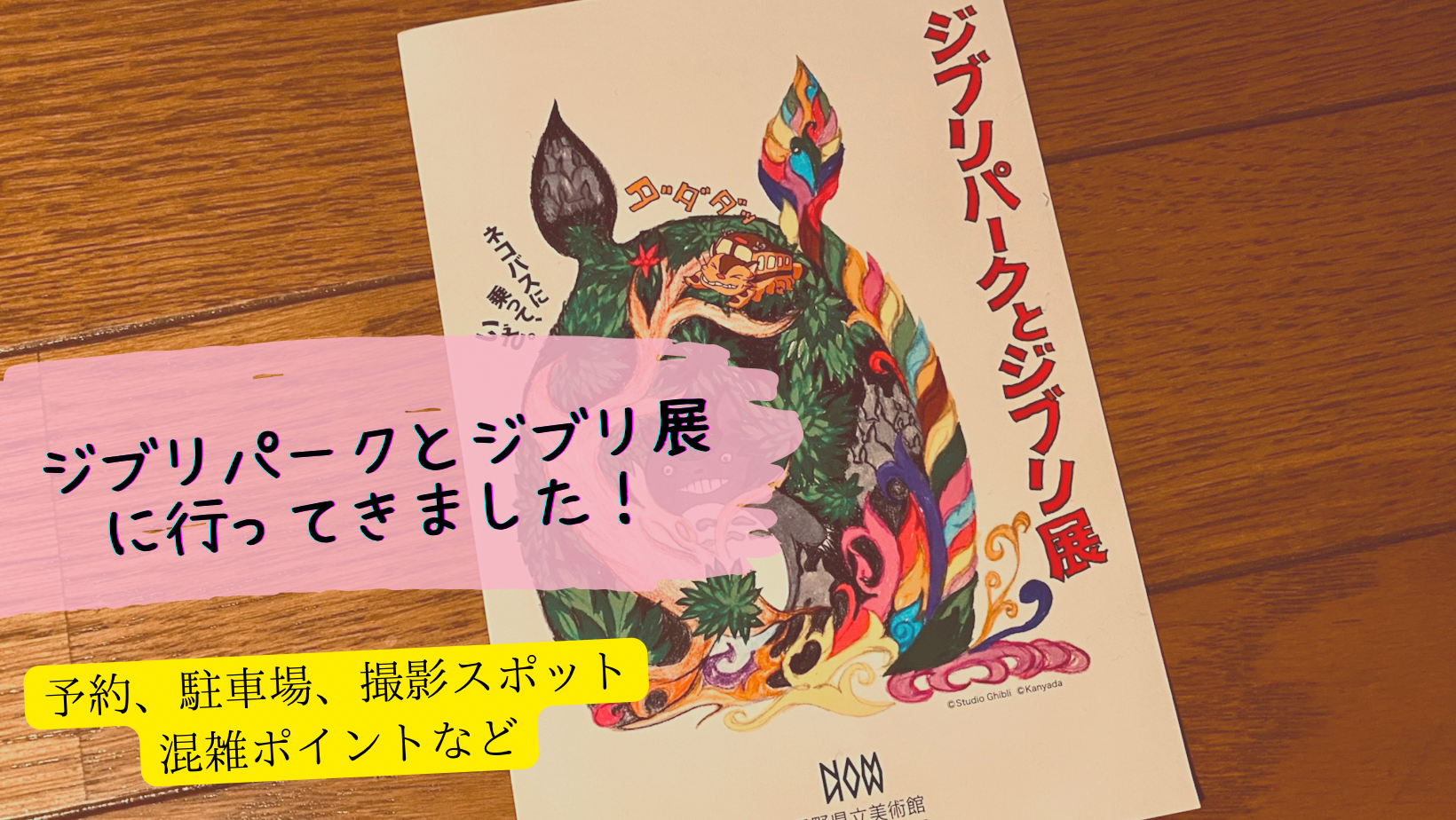野沢温泉の観光協会が毎年11月頃に行っている「野沢菜収穫・漬込み体験」に親子で参加してきました。野沢菜の収穫から温泉での泥洗い、漬込みまでを子供と楽しく体験できました。
目次
野沢温泉とは
長野の郷土料理「野沢菜漬け」に使われる「野沢菜」の発祥の地です。
元々当地では蕪菜と呼ばれていた野沢菜が、大正時代にスキー場がオープンすると全国から訪れたスキー客によって「野沢菜漬け」として広まったそうです。
また、古くから温泉地としても知られ、温泉街に点在する13の外湯(共同浴場)は江戸時代から湯仲間制度によって守られ、今も外湯巡りとして楽しむことができます。
野沢温泉は長野市街地から車で約1時間10分ほどの場所にあります。温泉街は道が狭く、駐車場を確保して徒歩やバス等の移動がおすすめです。
野沢温泉マウンテンリゾート観光局のイベント
たけのこ掘りやきのこ狩りなど、地方に住んでいてもなかなか体験できないような自然体験イベントを野沢温泉マウンテンリゾート観光局では定期的に開催しています。
詳細は、野沢温泉マウンテンリゾート観光局のトップページにあるイベントページから確認できます。
私は子供の通う幼稚園の配布物で知り、年中児でも参加可能とのことだったので親子で体験してきました。
野沢菜収穫・漬込み体験イベント
毎年11月頃に本場の野沢温泉で野沢菜を収穫して、温泉で泥洗いをし、1樽(約5kg)の時漬け(醤油漬け)を作る体験イベントです。
大まかなイベントの流れは以下です。
- 畑で野沢菜を収穫する
- 温泉で野沢菜を洗う
- 野沢菜を漬け込む
漬けた野沢菜漬けはそのまま持ち帰ることができ、希望すると郵送することも可能なので遠方に住む知人に手作りして送っても良さそうです。
1週間ほどで樽に水が上がってきたら(漬込みできたら)ジップロックに小分けにして冷凍すると最後までおいしく食べることができるそうです。
今回は私達を含めて3組のグループが参加しており、毎年参加されてるという年配のご夫婦、ソロ参加者、子連れの我が家でした。
イベント当日
野沢温泉までの移動
午後の回(13:00〜)に申し込みをし、朝は余裕を持って10:30に家を出ました。
車で国道117号線を新潟方面に進みます。
- 道の駅ふるさと豊田(中野市)
- 道の駅花の駅 千曲川(飯山市)
- 道の駅野沢温泉(野沢温泉村)
道中には道の駅がいくつかあり、トイレ休憩しやすく子連れに優しいルートでした。
12:15頃に野沢温泉の手前にある飯山市の道の駅「花の駅 千曲川」に到着。休日だったので食事処は1時間待ちの激混みで、同じく激混みの直売所でおにぎりとパンを買って外のベンチで食べました。
12:50に野沢温泉観光案内所に到着。車は駐車許可の紙を置いて裏手の農協に移動。参加費を支払ってマイクロバスに乗り込みました。
1.畑で野沢菜を収穫する

マイクロバスに乗って5分ほどで野沢菜の段々畑に到着。こちらは野沢温泉の村長さんの畑とのことでした。この日は快晴だったため雨具は使用せず作業に入りました。
初めて見た野沢菜は大人の腰の高さまで生い茂る大きさで、スーパーで販売されるほうれん草や小松菜と同じくらいのサイズを想像していた私には驚きでした。
野沢菜畑は秋の終わりにも関わらず青々としており、青空に向かって真っすぐ伸ばす葉はピンと伸ばしたウサギの耳のようで、近付く足音に聞き耳を立てているようでした。
野沢菜の収穫までの手順

- 畑から野沢菜を手前に抜く
- 野沢菜の根っこを切り落とす
- 野沢菜の葉先を切り落とす
- 野沢菜をテープで巻く
ここで重要なことは野沢菜を抜いたときに根に付いた泥を素早く切り落とし、他の野沢菜にかからないようにすることです。
野沢菜漬けをするとき、泥をきれいに落とすことが一番大変(泥が残ると漬物の口触りも悪くなる)なので、漬け込みに使用する野沢菜をいかに泥から守るかが重要だそうです。
畑から野沢菜を手前に引き抜いたら、包丁で根っこの泥をそぎ落とします。
野沢菜の長い葉は途中で切り落とし(私は少し短く切り過ぎてた)、テープで括れる量まで野沢菜を収穫しました。
野沢菜の根っこをそのまま食べてみる
野沢菜の根っこの部分は蕪(かぶ)のように丸く膨らんでおり、そのまま生で食べることもできるそうで一口食べてみると…
砂糖をまぶしたような甘さでした。
はつか大根のような触感ですが辛味やえぐみはなく、蕪をとても甘くしたような味でした。砂糖の原料になる砂糖大根もこんな味なのかなと思いつつ、野菜嫌いの娘も「おいしい。もっとちょうだい」と言って食べました(笑)
野沢菜漬けに根っこを入れても美味しいそうなのでなるべく根っこを残すように皮だけを削いでみました。市販の野沢菜漬けでは味わえないおいしさでした。
また、根っこは味噌汁に入れてもおいしいそうで、少し持ち帰らせていただきました。
2.温泉で野沢菜を洗う

収穫した野沢菜をマイクロバスに詰め込んで、野沢菜専用の温泉「なっぱ湯」へ移動します。
プラスチックのすのこを温泉の湯できれいに洗い流してから、すのこの手前半分に収穫してきた野沢菜を置き、温泉で洗った野沢菜は奥半分に置きます。
根っこの部分を温泉に浸して茎を一つ一つ優しく開いて茎の間に入った土を洗い流します。温かい温泉が気持ちいいです。
野沢菜は冷たい水で洗うものとばかりに思っていたので、野沢菜漬け発祥地ならではの「なっぱ湯」の存在には驚きました。
毎年参加されてるご夫婦によると以前は寒い山の中で洗ってたそうですが、今は移転して環境もよくなったそうです。この日は快晴なこともあり温かいお湯で野沢菜を洗う内に少しウトウトして眠くなりました。
洗った野沢菜はテープで括り、またマイクロバスに乗せて集合場所の野沢温泉観光案内所に戻りました。
また子供はこの時点で洋服がお湯でぐっしょり湿っていて、念の為に用意していた着替えに着せ替えました。
3.野沢菜を漬け込む

野沢温泉観光案内所の一室に用意された樽、まな板と包丁、塩昆布を使っていよいよ漬け込み作業です。
最初に野沢菜のしょうゆ漬けを試食します。
緑のお野菜が苦手な娘も「おいしい」と言ってパクパク食べてました。
いよいよ、漬け込み作業。
樽に漬物用のビニール袋を広げ、野沢菜を食べやすい大きさ(3〜4cmくらい)にぶつ切りしては放り込みます。時々、塩昆布も1つまみ入れます。
大量の野沢菜をひたすらぶつ切りにする作業は今回のイベントで一番きつい作業でした。
野沢菜をすべて切って袋に入れたあとは、袋を取り出し、袋の先を手で掴み、野沢菜と塩昆布を馴染ませるように袋を両手で持ち上げてよく振ります。
そして袋を樽に戻して、漬物用のタレを入れます。
ここでは予め調味料を混ぜ合わせたものがペットボトルに入って用意されているのでそれを投入。全体に馴染ませたら完成です。
※タレのレシピは紙でも配布されました
野沢菜漬けは1週間で食べ頃に
野沢菜漬けを持ち帰って1週間。漬けダレが袋の上の口まで上がってきており、食べ頃になりました。
味見をするとご飯が欲しくなる美味しさ。ちょっと甘じょっぱくて、娘も「もっとたべたい」とねだります。
すぐにタッパー1個分を残して、残りをジップロックに小分けして冷凍保存しました。小分けした野沢菜漬けは冷蔵庫で自然解凍すれば美味しく食べられるそうです。
さいごに
野沢温泉の野沢菜漬けの体験イベントは、娘が最初から最後まで飽きずに楽しめたこと、少人数なのでそれぞれのペースでできたこと、帰ってきたあとも野沢菜漬けを食べて楽しめること、など満足度が高いイベントでした。
来年も野沢温泉の宿泊もセットで楽しめたらと思います。