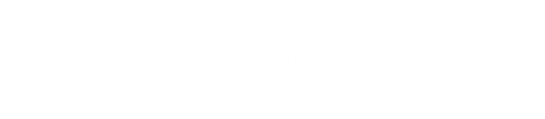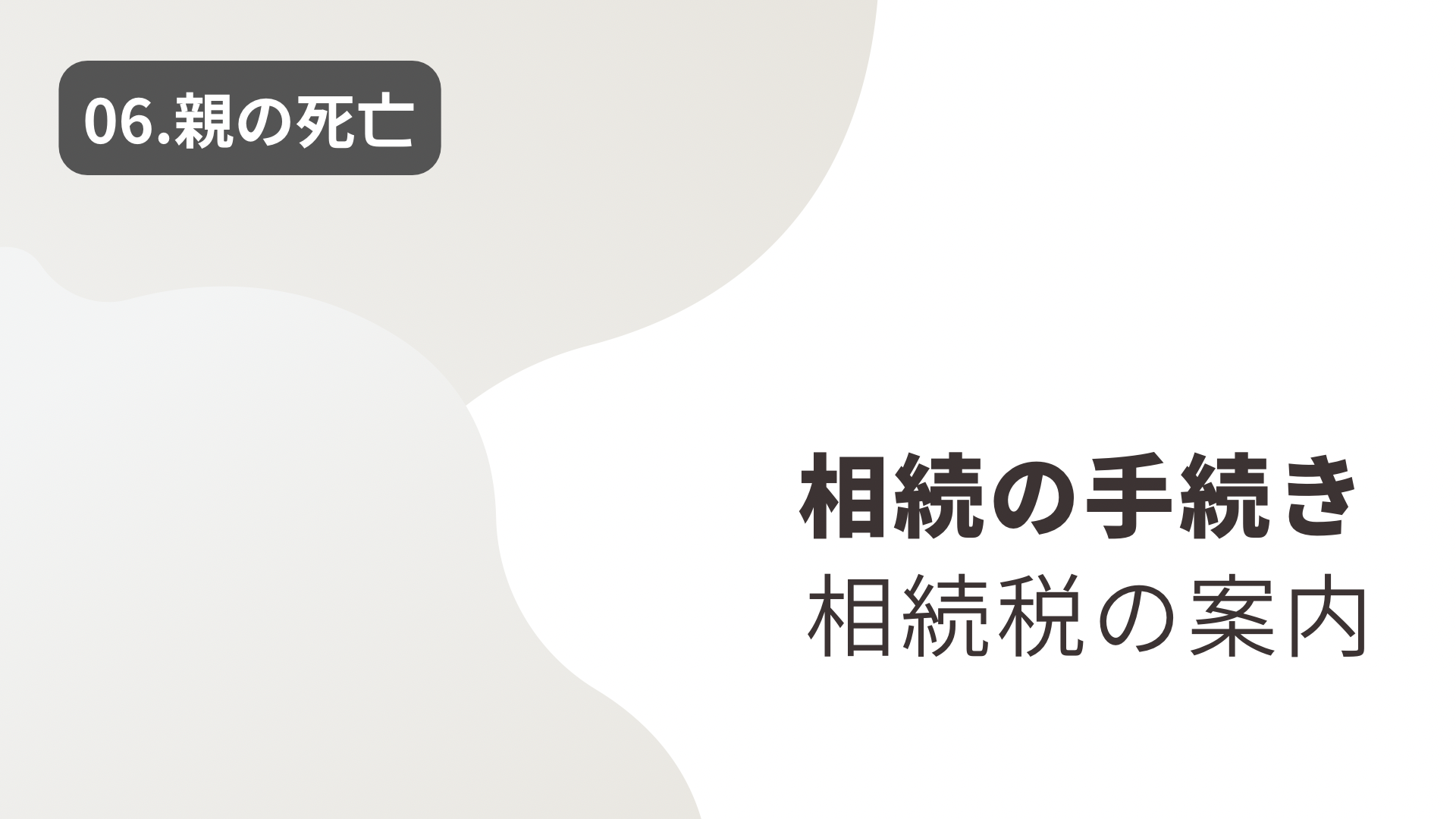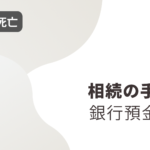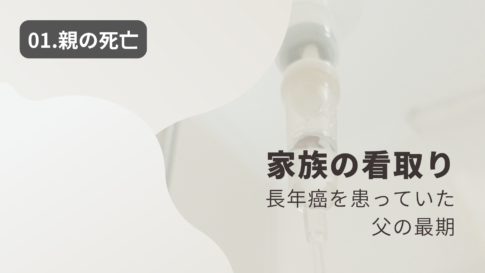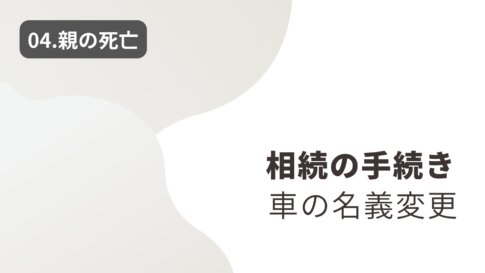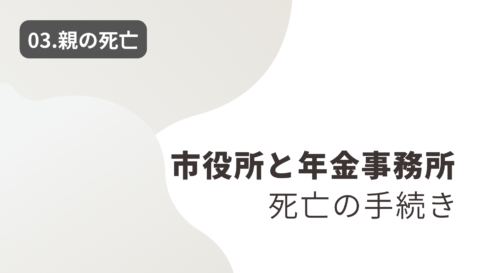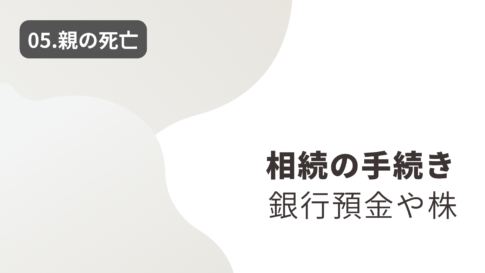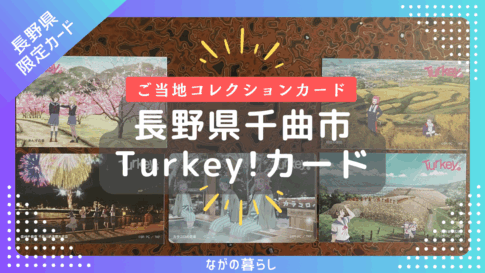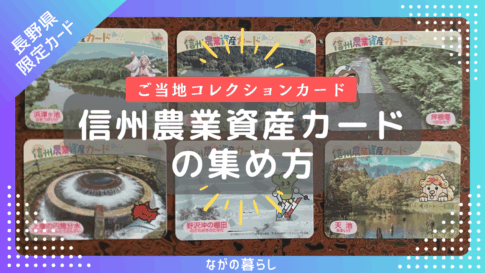税務署から母宛に死んだ父の「相続についての申告等の御案内」があり、書類の提出期限が切れていたので慌てて税務署に提出してきました。
「相続についてのお尋ね」とは
「相続についてのお尋ね」は税務署に提出する書類で、以下の項目があります。
- 亡くなられた人の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、亡くなられた日を記入してください。
- 亡くなられた人の職業及びお勤め先の名称を「亡くなる直前」と「それ以前(生前の主な職業)」に分けて具体的に記入してください。
- 相続人は何人いますか。相続人の氏名と亡くなられた人との続柄を記入してください。
- 亡くなられた人や先代名義の不動産がありましたら、土地、建物を区分して(面積は概算でも結構です。)記入してください。
- 亡くなられた人の株式、公社債、投資信託等がありましたら記入してください(亡くなった日現在の状況について記入してください。)。
- 亡くなられた人の預貯金・現金について記入してください(亡くなった日現在の状況について記入してください。)。
- 相続人などが受け取られた生命(損害)保険金や死亡退職金について記入してください。
- 亡くなられた人の財産で、上記4から7以外の財産(家庭用財産、自動車、貸付金、書画・骨とうなど)について記入してください。
- 亡くなられた人から、相続時積算課税を適用した財産の贈与を受けた人がおられる場合に、その財産について記入してください。
- 亡くなられた人から、亡くなる前3年以内に、上記9以外の財産の贈与を受けた人がおられる場合に、その財産について記入してください。
- 亡くなられた人の借入金や未納となっている税金などの債務について記入してください。また、葬式費用について記入してください。
- 相続税の申告書の提出が必要かどうかについて検討します。(概算によるものですので、詳細については税務署にお尋ねください。)
「相続についてのお尋ね」へ記入する
父は80歳を超えた年金受給者で、相続人は妻と子供2人の合計3人です。
不動産はなく、株式と銀行預金があり、債務としてクレジットカードの未払金がありました。
そのため、「相続についてのお尋ね」の項目1〜3、5、6、11、12を、以下の相続関連書類と照らし合わせながら記入しました。
相続関連書類
- 法定相続情報一覧図
- 証券会社の相続株式
- 銀行の相続手続完了書類
- 父名義のクレジットカードの振込依頼書の控え
- 葬儀費用の領収書
父の相続税は発生しない見通し
事前に税理士に相談して相続税はかからないと聞いていたので、「相続についての申告等の御案内」が届いたことに驚きました。
「相続についてのお尋ね」を記入すると、最後の12項目に相続税の基礎控除額の計算式があり、
基礎控除3,000万円+(相続人3人×600万円)=4,800万円
となり、基礎控除額を超える相続はないので相続税は発生しない見通しです。
相続税の未払いの督促というより、確認のために送られてきたようです。
税務署の窓口へ提出する
税務署の窓口へ行き、受付で「相続税についての申告等についての御案内」を見せ、記入書類に問題ないか確認をお願いしました。
(事前予約したほうがいいかもしれません)
受付番号を渡され、しばらく待つと自分の番号が呼ばれます。
税務署の方に記入した「相続についてのお尋ね」を渡し、記入時に使用した相続関連書類を見せました。
入力内容は問題ないとのことでした。
その後、記入漏れがないか口頭で相続や財産状況について確認され、無事に提出できました。
死亡から4ヶ月以内に確定申告が必要
税務署の窓口で死んだ父の確定申告のことを聞くと、どうも家族が死んだ場合はその死亡を知ったときから4ヶ月以内に確定申告が必要なようでした。
すっかり失念してました。
父の場合は年金受給者で、それ以外の収入が株式投資となり、死んだ年は売買はしておらず、配当金は源泉徴収されているので、確定申告しなくても問題はなさそうだとのことでした。
どちらかというと払い過ぎた税金の還付のために確定申告が必要かもしれません…
提出期限の過ぎた「相続についてのお尋ね」が無事提出でき、これで死亡手続きが一段落するといいです。